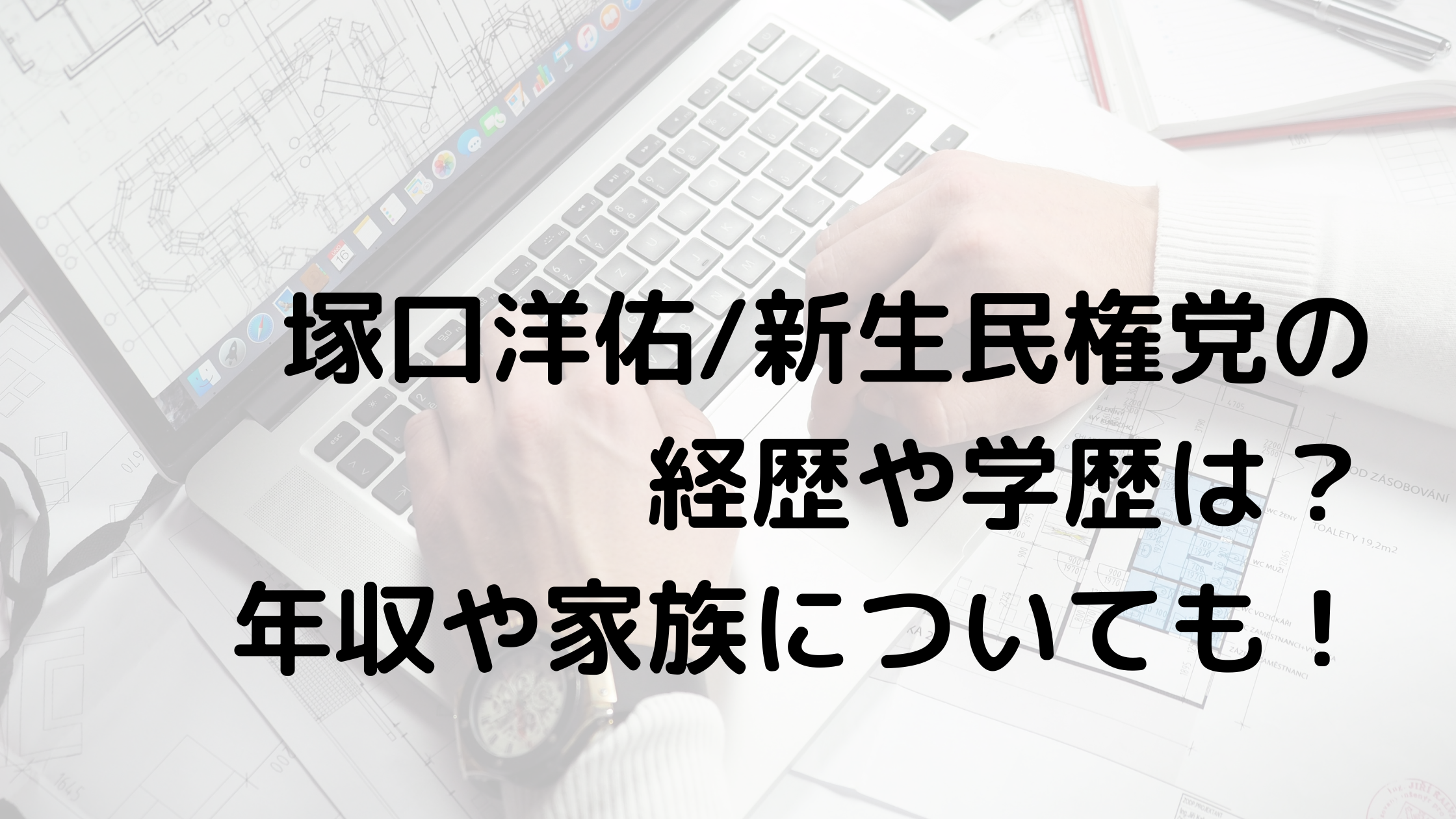今回の記事では、報道番組「ABEMA Prime(アベマプライム)」出演や新生民権党活動などで話題の塚口洋佑氏について記事をまとめていこうと思います。
塚口洋佑氏の
- 経歴
- 学歴
- 年収
- 家族
などについて記事をまとめていきます。
塚口洋佑/新生民権党の経歴や学歴は?
塚口洋佑氏の経歴や学歴についてまとめていきます。
塚口洋佑の経歴は?
| 名前 | 塚口洋佑(つかぐちようすけ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年 |
| 身長 | 不明 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 最終学歴 | 京都精華美術大学中退 |
| 職業 | 新生民権党代表 |
塚口洋佑氏は、X 新生民権党 塚口洋祐や塚口洋佑(新生民権党代表)で政治問題や社会問題について多くの情報を発信されています。
プライベートに関しての情報は少ないですが、過去に出版業に携われていた情報が見つかりました。
また、著者名が塚口洋佑で出版された書籍「メジャーリーグのバッティング技術」も確認できました。
著者プロフィールには、大阪府吹田市の少年野球チームに所属、高校ではソフトボールを経験、フリーターをしながらスポーツバイオメカニクスやバッティング理論を独自に研究したことが掲載されています。
出版本の著者プロフィールには大阪府出身とあり、「日章新聞」の取材記事でも出身地が大阪であることが確認できました。
日章新聞の記事によると、塚口洋佑氏はアメリカ同時多発テロをきっかけに陰謀論に関する活動を始められたようです。
その後コロナの流行を受け、2020年4月より反コロナを掲げて社会活動を開始。
2022年には政治団体「自由と平和をつかむ党」を立ち上げ、代表を務められています。
翌年2023年に、目指す政策を反コロナに絞り、川崎市議会議員選挙多摩区選挙区に立候補。584票で落選となりました。
以降、党名を「新生民権党」に改称し、日本独立を主軸として政治活動を継続。
2025年2月には財務省解体を掲げた千人規模のデモが話題にもなりました。
私の主催した財務省前デモが、特に悪意ある切り取り無しにTVで放送されました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。日本を外資株主に売り渡すグローバリズムの悪き経済政策は何としても辞めさせなければいけません。返信欄に当日の動画など貼り付けていきます。 pic.twitter.com/f3Aky8zx7T
— 新生民権党 塚口洋佑 (@shinseiminkento) February 22, 2025
塚口洋佑氏は、貧困に苦しむ現状を変えたいという信念で、SNSを中心に精力的に活動されているようです。
塚口洋佑/新生民権党の本名は?
塚口洋佑氏の本名についての情報は確認できませんでした…。
塚口洋佑/新生民権党の学歴は?
塚口洋佑氏の学歴は、著書のプロフィールに北千里高校卒、京都精華美術大学中退と掲載がありました。
塚口洋佑の出身高校は?
北千里高校は大阪府吹田市にある公立高校です。
生徒の進路に合わせた少人数授業や、より深い学びのための学習強化週間が設けられており、卒業生の多数が大学進学する進学校として知られています。
多彩な学習への取り組みとして、気象予報士や中国音楽演奏家による特別授業なども行われるようです。
塚口洋佑の出身大学は?
京都精華美術大学は、京都府京都市にある私立大学です。
国際文化学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部の5つの学部が設置された、表現の総合大学として知られています。
マンガ学部が日本で初めて設置された大学で、京都国際漫画ミュージアムの開設など、マンガの研究や保全にも力を入れているようです。
また、新しい教育システムの構築も行われており、文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」に複数回採択されている有名大学です。
塚口洋佑/新生民権党の仕事は?
塚口洋佑氏は新生民権党の代表を務められています。
YouTube新生民権党オフィシャルでは、新生民権党は消費税撤廃と社会保険料半減、憲法第9条改正を訴えています。
国民のお金と個人の尊重を大切にし、他の国に左右されない、独立した日本の政治を目指した政党のようです。
塚口洋佑/新生民権党の家族は?
塚口洋佑氏のご家族についての情報は確認できませんでした…。
塚口洋佑/新生民権党の年収や月収は?
塚口洋佑氏は現在、新生民権党の代表を務められていますが、給与が発生する仕事についての情報は確認できませんでした…。
まとめ
今回の記事では、塚口洋佑氏について記事をまとめてみました。
塚口氏はSNSを活用し、精力的に活動を続けられています。
地道な情報発信や街宣活動により、国民の本当の声を代弁し国政を変えてくれる人物として、期待を寄せる人も多く見られます。
また、塚口氏に賛同するデモ参加者も増え、運動は全国に広がっています。
塚口氏の活動により、国民の本当の声が反映された国政となるのか、これからの動向に注目していきたいですね。